こどもに手間をかけずお薬を飲んでもらう方法
みなさんはお子さんにお薬を飲ませる事に苦労されていませんか?
こどもは薬の何が嫌で飲まないのか?なかなか理解できない事が多いかと思います。
今回はお子さんに出来るだけ苦にならずにお薬を飲んでもらえる方法をご紹介します。

お薬を上手に飲ませる・使うために知っておいてほしいことを紹介します。
①お薬を上手に飲めたときはほめてあげましょう
ほめてもらうと子どもは嬉しくなり、次も嫌がらずにお薬を飲むようになることがあります。また、お薬を飲めないとつい叱ってしまいがちですが、叱られたことでそれが嫌な思い出となってしまい、お薬が嫌いになってしまうことがありますので気を付けましょう。
②お子さまにお薬を使う理由を話してみましょう
理由を理解することで、お薬をきちんと使えるようになることがあります。また、お薬を使って症状がよくなったら、「お薬を使ったからよくなったんだよ」と伝えておくことも効果的です。
③お薬によっては、剤形(粉薬・シロップ薬・錠剤など)を選ぶことができるものもあります
お子さまが好む剤形がある場合は、あらかじめ医師に伝えておきましょう。
④アレルギーの確認
お薬を飲んでアレルギー反応や副作用が現れるなど、からだに合わない薬があった場合や、食べ物アレルギーがある場合は、そのお薬や食べ物の 名前をおくすり手帳に記入しておき、受診時に医師に見せましょう。
お薬をいつ飲ませたらよいか
【新生児、乳児の場合】
1日3回のお薬は、おおよそ朝・昼・夕の5~6時間間隔で、授乳時など に合わせて飲ませます。
【幼児の場合】
1日2回のお薬は、朝と夕(例えば朝7時頃、夜7時頃)、1日3回のお薬 は起きている時間を3等分して(例えば朝8時頃、昼2時頃、夜8時頃)飲ませます。
保育園や幼稚園などの事情により昼飲めない場合には、行く前と帰ってからと寝る前などのように3回飲ませるといった方法もあります。なお、保育園の帰りが遅いなどで時間が合わない場合は、1日2回飲ませれば よいお薬もありますので医師に相談してみてください。
- 粉くすり・水くすり
①粉くすりの袋をあける前にトントンたたいて一方の端に寄せておく。
②水(シロップ)を、スポイトで少しずつ落としながらまぜる。
③スポイトで吸い上げて飲ませる。
- 錠剤・カプセル剤
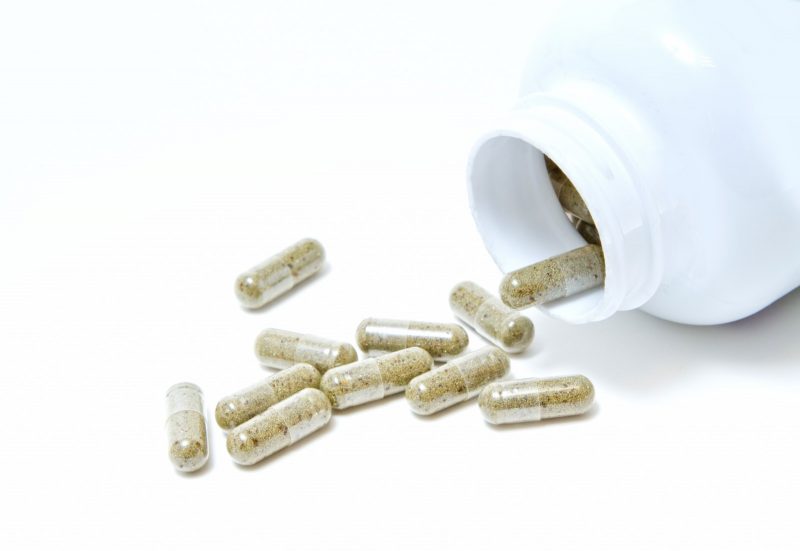
少しの水を口に含み、上を向かせ、1粒ずつ口の中に入れ、タイミングを取りながらゴックンさせることが基本の飲ませ方となります。錠剤やカプセル剤は口の中で上に浮いてしますので、飲み込むタイミングの時に「下を向かせながらゴックン」させると食道に流れ込みやすくなりますので、チャレンジしてみて下さい。
- 1日3回食後という指示がされていても、こどもの食事は不定期になりがちなので、特別な薬でない限りは食前でもかまいません。
- 飲ませるのを忘れたときは、次に2回分飲ませるのではなく、1回分にしてください。
- ミルク、おかゆ、とうふなど、主な栄養源となっている食品とは、決してまぜないようにしてください。味が変わって飲み残したり、ミルク嫌い、ごはん嫌いになったりするおそれがあります。また、炭酸飲料やスポーツドリンク、果汁の多いジュースなどは、お薬の吸 収や効果に影響を与えてしまうので、混ぜないでください。
- 《早く良くなるためにちゃんと飲もうね》と、声をかけながら飲ませてください。
- 飲めなくても怒らない、飲めたら必ずほめてください。
おススメのおくすりの飲ませかた
味や香りが強いものはお薬の味を感じさせることなく飲ませることができます。例)ヨーグルト、アイスクリーム*、ジャム、プリン、ジュース、 チョコレートクリーム、コンデンスミルクなど*アイスクリームは、舌を冷やし、一時的に神経を麻痺させて、味を感じ にくくします。 お薬によっては飲食物を混ぜると逆に苦味が増して飲みにくくなったり、 お薬の効果が弱くなったりするものもあります。またお薬用ゼリーのオブラート、特にチョコレート味は、抗生物質などのニガイくすりの味や臭いを包んで、小さなお子様にもつるりと飲ませることができます。お薬用ゼリーは離乳中期から使用できる、乳児用規格適用食品です。
お薬団子の作り方
- 1回分の粉薬をお皿にあけ、1~2滴の水をおとして、団子状に固めます。
- 水が少ないときは、1滴ずつ足して、多すぎたらクリープや調整ココアなどをまぜて、固めます。
- お子さんが飲みこめる大きさに分けて、口に入れ、すぐに好きな飲料を、飲ませてください。それでも飲みにくいときは、お団子をプリンやヨーグルトに1粒ずつ入れて飲みこませてください。
- どうしても飲めない子には、チョコを刻んで湯せんで溶かし、くすりを入れて成型し、冷蔵庫で固めて、チョコ団子にして飲ませる方法もあります。
今回は専門家の文献を参考に、お子さまへの「お薬の飲ませ方」について紹介させていただきました。
参考文献:JA 北海道厚生連旭川厚生病院 薬剤部
埼玉県薬剤師会
関連学科
こども保育科 2年制【2027年4月募集再開予定】
高校卒業以上の方
国家資格:保育士
作業療法士科 4年制【高度専門士】
高校卒業以上
国家資格:作業療法士、幼稚園教諭
-
こどもに関わる作業療法士になるなら!
- こども専攻
コラム:カテゴリー
保育士コラム:タグ
お薬こども乳児保育保育幼児保育





