作業療法士と理学療法士って何が違うの?~歴史の違いと日常の会話から~
【前説】
アメリカのなりたい職業ランキングで作業療法士は度々上位にランクインしますが、日本ではそこまで知名度が高くありません。筆者の体験でも初めて知り合った人に「作業療法士をしています」と言うと、「介護ですか?」と返されることがよくあります。あるアンケート調査では、作業療法士を知っている人は63.6%、仕事内容を知っている人は22%と報告されており一般的認知の低さが伺えます。作業療法士という仕事を知るきっかけでよくあるのが「理学療法士になろうと思って調べるうちに作業療法士を知った。」というパターンです。そして、「知れば知るほど作業療法士の方が自分に合っているような気がして、理学療法士ではなく作業療法士にしました。」と言う受験生は少なくなく、いつも私は心の中でガッツポーズをしています。この「知れば知るほど」という言葉に一言では語れない作業療法士の仕事の奥深さと魅力が表れている一方で、仕事が理解されづらい理由でもあると思います。
そこで今回は、これまで理学療法士とともに日本のリハビリを支えてきた作業療法士がどのような仕事を担っており、両者は日常的にどのようなコミュニケーションをとっているのかをご紹介します。
目次
1、作業療法士という仕事
2、作業療法士と理学療法士の協働
3、作業療法士と理学療法士の会話
4、まとめ
1、作業療法士って何者!?
多くの人は「リハビリ」という言葉から運動療法をイメージするのではないでしょうか。テレビでは一生懸命歩くリハビリのシーンを度々目にしますし、理学療法が運動療法とともに発展してきたためそのような印象になっても仕方ありません。しかし、作業療法はその概念から一線を画し、精神医療から派生した歴史があります。精神疾患の入院患者に対して仕事や余暇など(作業活動)を通して自律的で規則正しい生活を送る中で心の改善を図ったことが作業療法の起源とされており、19世紀初頭に呉秀三という精神科医が作業療法を持ち込み、1965年に国家資格化されました。また、当初は作業をリハビリの手段として用いる考え方でしたが、今では対象者にとって価値のある生活行為を作業と捉えており、作業は手段ではなく作業療法の目的・目標そのものという認識に変化しています。(図1)

現在、作業療法士は理学療法士・言語聴覚士とともに日本のリハビリテーションの一翼を担い、子どもから高齢者、心や身体に障害を抱える方々の「作業」の再建を目指して様々なところで生活行為の治療支援をしています。
| 1-1-1理学療法士及び作業療法士(昭和40年法律第137号:1965年) |
| この法律で『作業療法』とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせることをいう。 |
| 1-1-2社団法人 日本作業療法士協会による『作業療法』の旧定義(1985~2018) |
| 作業療法とは、身体又は精神に障害のある者、またはそれが予測される者に対し、その主体的な生活の獲得を図るため、諸機能の回復、維持及び開発を促す作業活動を用いて、治療、指導及び援助を行うことをいう。 |
| 1-1-3一般社団法人 日本作業療法士協会による『作業療法』の定義(2018) |
| 作業療法は、人々の健康と幸福を促進するために、医療、保健、福祉、教育、職業などの領域で行われる、作業に焦点を当てた治療、指導、援助である。作業とは、対象となる人々にとって目的や価値を持つ生活行為を指す。
(注釈) ・作業療法は『人は作業を通して健康や幸福になる』という基本理念と学術的根拠に基づいて行われる。 ・作業療法の対象となる人々とは、身体、精神、発達、高齢期の障害や、環境への不適応により、日々の作業に困難が生じている。またはそれが予測される人や集団を指す。 ・作業には、日常生活活動、家事、仕事、趣味、遊び、対人交流、休養など、人が営む生活活動と、それを行うのに必要な心身の活動が含まれる。 ・作業には、人々ができるようになりたいこと、できる必要があること、できることが期待されていることなど、個別的な目的や価値が含まれる。 ・作業に焦点を当てた実践には、心身機能の回復、維持、あるいは低下を予防する手段としての作業の利用と、その作業自体を練習し、できるようにしていくという目的として作業の利用、およびこれらを達成するための環境への働きかけが含まれる。 |
図1.国内における作業療法定義の遍歴
2、作業療法士と理学療法士の仕事の住み分け
身体障害に対するリハビリを例にお話します。身体障害分野の病院・施設であれば、たいてい作業療法士と理学療法士が勤務をしています。近年では訪問リハビリと言って、対象者様のご自宅でリハビリをするというサービスも増えています。
病院には内科や外科など様々な診療科目があり、その中でも作業療法士と理学療法士は「リハビリテーション科/部」という診療科に所属しています。スタッフ数は平均すると総勢30~50名ほどで、リハビリテーション病院ともなると100名を超える人数になります。作業療法・理学療法は医師から処方箋がリハビリテーション科に出されて開始されます。お薬を出すときのあの処方箋と一緒です。処方箋の指示のもと、部署内で作業療法・理学療法のそれぞれの担当者を決めます。
ここから協働作業の開始です。まずはそれぞれの専門的な視点で患者様の状態の評価をします。理学療法士は座る・立つ・歩くなどの基本的な運動がどの程度できるのかを評価します。作業療法士は身体面、知的面から日常生活に必要な活動がどのくらいできるのかを評価します。また入院前の状態にも目を向け、どのような生活をしていたのか、仕事は?、趣味的な活動は?などを聴取し、リハビリで何が出来るようになりたいか、何を出来るようにならないといけないかなどを対話していきます。
両者の評価が終了するとリハビリテーション目標を考えます。例えば「身の回りのことは自分でおこなえて、近所へ買い物する程度の屋外移動能力を身につける」と目標にしたのならば、理学療法では「近所を移動できる歩行能力や体力の獲得」を目標とし、作業療法では「日常生活で必要な身辺活動の獲得、買い物で必要な能力の獲得」が目標になったりします。買い物に必要な能力とは例えば、物を取る、買い物カゴへ入れるなどの動作、買い物の計画やお金の管理など知的な能力を指します。病院や施設ではほぼ毎日リハビリテーションが実施されており、日々の変化を捉えるためには担当者同士のコミュニケーションが大切となります。
3、作業療法士と理学療法士の会話
理学療法士 「杖を使えば100mくらいは安定して歩けるようになってきたよ。」
作業療法士 「だいぶ歩けるようになったね。自信がついてきたって喜んでたよ。500mくらい歩ければ、買い物をして帰ってこれそうだね。」
理学療法士 「そうだね。そこまで歩けるようになるにはもう少し時間がかかりそう。そういえば歩いている、ときは周りへ注意を向けられない場面があるんだ。外は他にも歩行者はいるし、信号があれば止まらないといけないし、周囲へ注意を向けられないと危ないんだよね。」
作業療法士 「歩くことだけで精一杯なのかもしれないね。でも注意力の検査では2つのことを同時に行いながら注意を払う能力の低下が見られたからそれも影響している可能性があるよ。」
理学療法士 「なるほど、確かに他の場面でも1つのことに集中して他に目を向けられていないことがあるねどうしたらいいかな?」
作業療法士 「まだ歩きながら周囲に注意を払うことはレベルが高いと思うから、まずは立ちながら注意を払う課題をしてみたら良いと思う。例えば輪投げをして、立位バランスをとりながら輪を的に入れることにも注意を向けるとか。次の作業療法から取り入れるよ。」
理学療法士 「ありがとう。また様子を教えてね。」
このような場面はスタッフルームでよくある会話です。お互いの進捗状況の確認をしながら、場合によってはリハビリテーションプログラムの微調整をしていきます。作業療法と理学療法の専門性は異なりますが、患者様のリハビリテーション目標を達成に向けて、それぞれが専門性を発揮するということが大切になります。
4、まとめ
今回は歴史的背景と身体障害領域での日常から作業療法と理学療法士の仕事を紹介させて頂きました。前段でお話した通り、作業療法はひとの生活行為すべてを作業と捉えています。対象者にとって価値のある作業を取り戻すためには身体面や精神面・知的面の理解が必要であり、対象者のこれまでの生活習慣や価値観なども把握して包括的にリハビリを考えなければなりません。そうするためには体の構造や病気・障害などの医学的知識はもちろんですが、ひとの生活そのものをよく知っておく必要があります。
東京福祉専門学校では「ひとの生活と作業」というオリジナル科目があり、当たり前のように過ごしている日常を紐解いてひとの生活にはどのような意味があるのかを考えていきます。それに加えて、手芸・陶芸・木工・各種ゲーム・スポーツ・音楽など様々な体験を行う「圧倒的作業体験」というプログラムで作業の価値を考えていきます。
作業療法士が行うリハビリの広さや深さに興味がありましたら是非一度オープンキャンパスにお越し下さい。

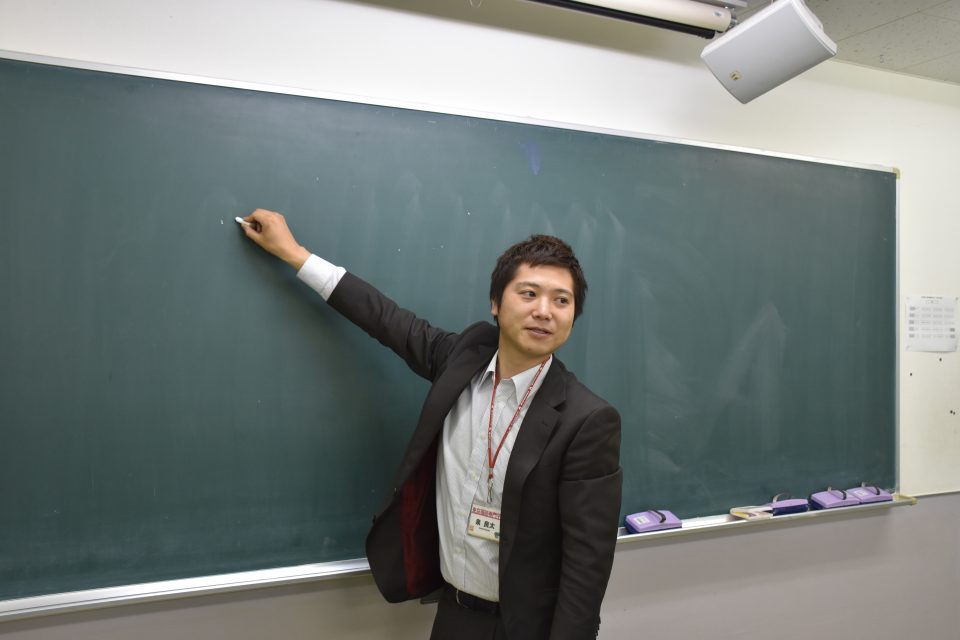







泉 良太 先生
東京福祉専門学校の卒業生。 卒業後、都内の救急病院で作業療法士として責任者を勤め、その傍らで大学、専門学校の非常勤講師として活躍。 スタッフへのマネージメントや教育をしていく中で教育に気持ちが入り専門学校の教員に転身。
座右の銘:雲の向こうはいつも青空